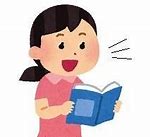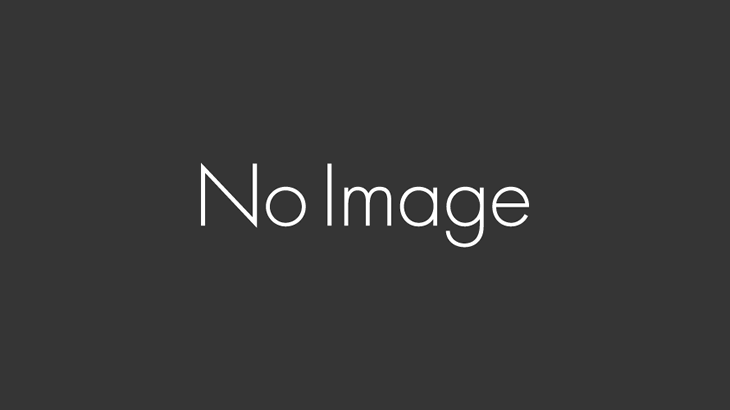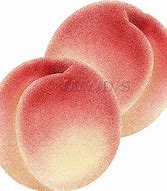こんにちは。明日は冬至ですね😄
冬至について調べてみました。
冬至とは24節気の一つで、1年で夜が最も長く昼が短い日です。冬至は天文学的にいうと、太陽の黄経(こうけい)が270度に達する日で、太陽が一番南にある状態です。そのため、北半球では1年中で昼がいちばん短く、夜がいちばん長くなる日を意味するんです。二十四節気は日付固定ではないので、日付は変動します。また、12月22日から次の二十四節気の第23節、小寒の2022年1月5日までの15日間ぐらいを指します。
✨冬至にカボチャを食べるのはどうして?
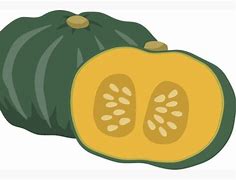
冬至の日には、「ん」のつくものを食べることで「運」を呼ぶことができると言われています。
かぼちゃは、漢字で書くと南瓜(なんきん)。
縁起かつぎとして、冬至にかぼちゃが食べられるようになったそうです。
一説では、「ん」はいろはの最後の文字であることから「ん」のつくものを食べるのには「一陽来復」の意味が込められているとも言われています。
また、かぼちゃは夏から秋にかけて旬を迎える食材でありながら、保存がきき栄養豊富なことから、昔から冬にも食べられていた食材。
冬至にかぼちゃを食べるのは縁起をかつぐ意味だけでなく、栄養をつけて寒い冬を乗り切ろうという意味も込められているそうです。
✨ゆず湯に入る

翌日から日が長くなることから、冬至は運気が上昇に転じる日と考えられており、「一陽来復」という考えがありました。
そして、運を呼び込む前の厄払いとして、古来より魔除けの色とされていた黄色いゆずを入れたお風呂に入るようになったと言われています。また、香りの強いゆずのもとでは邪気が起こらないという考えもあったそうです。
ほかにも、ゆず=「融通が利く」、冬至=「湯治」といった語呂合わせは縁起がよいとされ、冬至にゆず湯に入る習慣が根付いたとも伝えられています。
元気な身体で冬を越したいですね❄☃
元気に過ごすために、お身体で気になることがあればほほえみ接骨院にご来院ください🍀